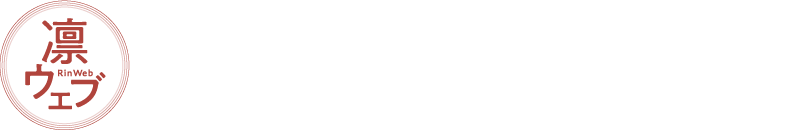奨学金のお知らせ
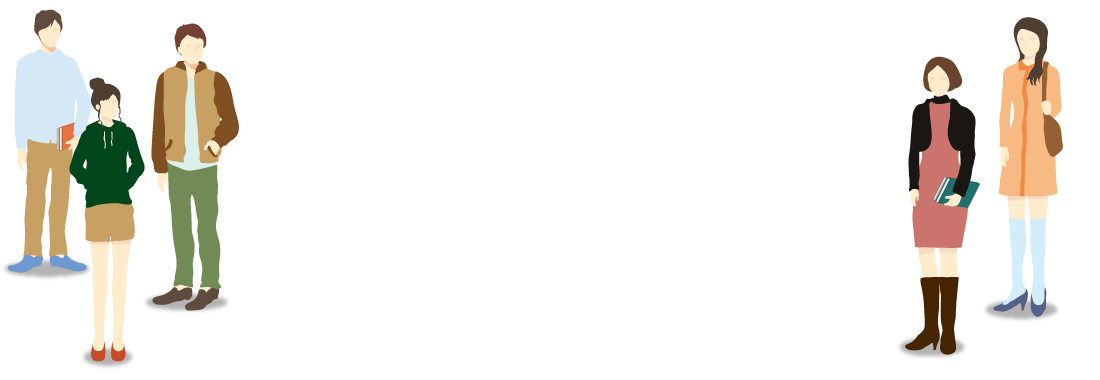
高等教育修学支援新制度の「新たに生まれた子等」の取扱いにおける対象範囲の拡大に係る手続きについて(住民税情報で確認できない「扶養する子」の確認)
2025.9.16
学生 各位
表題の件について、日本学生支援機構から通知がありましたので、お知らせします。
対象となる学生は学生課に申告し(※1)、期限までに必要書類を提出してください。
まずは、項目2.『本取扱いにおいて新たに対象とする者』で、自分が対象者であるか確認してください。
※1 申告した方に、関係書類をお渡しします。早めに学生課までご連絡ください。
1.通知の概要
修学支援新制度における多子世帯に該当するかの判定では、「扶養する子」の数を原則として住民税情報により確認しており、2025年度からは、住民税情報に反映されない一定の期間(後述する「追加判定期間」)内に生まれた子等を「扶養する子」に含めて判定することとしたところです。
このたび、追加判定期間内に発生した事由により、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子についても、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合は「扶養する子」として計上し、多子世帯の判定をすることといたします。
本取扱いの対象となる手続きは、2025年4月から9月までの支援区分について多子世帯と判定されなかった(※2)が、追加判定期間において本取扱いの対象範囲の拡大により要件を満たす場合、2025年4月に遡り判定を適用します。2025年度秋の手続き(適格認定(家計)、在学二次採用)については、要件を満たす場合、2025年10月から判定を適用します。
※2 第Ⅰ区分から第Ⅳ区分であるが多子世帯と判定されなかった者や、2025年春(在学一次)採用及び家計急変採用において不採用となった者を含みます。
2.本取扱いにおいて新たに対象とする者
次の①、②のいずれにも該当する者 (表1参照)
①対象となる奨学金手続き該当者
②対象となる事由発生の期間(追加判定期間)に生計維持者に死別・離婚・暴力等からの避難等の扶養の異動を伴う事実があり、生計維持者の「扶養する子」の数が3人以上であることが公的証明書類等により確認できる者
※ 判定の際に用いる住民税情報には扶養の状況が反映されていないものの、その後反映されると考えられるもの(蓋然性が高いと認められるもの)を想定しています。
※ 例えば、生計維持者(父母)2名のうち1名が子供3人を扶養する家庭で、その後の追加判定期間にその扶養者が死去し、もう一方の生計維持者が子供3人を扶養することになっても、判定に用いる住民税情報ではその状況を確認できないことがあります。このような場合に、現在の生計維持者による扶養の実態を公的証明書類により確認することを想定しています。
※ 離婚調停中など追加判定期間中の事由の発生が認められなくとも、暴力等からの避難等を伴う場合等。
【表1】
| 対象となる奨学金手続き | 判定が適用される 支援期間の始期 |
対象となる事由発生期間 (追加判定期間) |
必要書類の 学生課提出期限【注】 |
|---|---|---|---|
| ア. 2024年度以前採用者(既採用者)に係る 2025年4月以降の支援区分見直し |
2025年4月 | 2024年1月1日~ 2025年3月31日 |
2025年9月26日 |
| イ. 2025年度給付奨学生採用候補者(高校予約)の 進学届提出による採用 |
2025年4月 | 2024年1月1日~ 2025年3月31日 |
2025年9月26日 |
| ウ. 2025年度春の在学定期(一次)採用 | 2025年4月 | 2024年1月1日~ 2025年3月31日 |
2025年9月26日 |
| エ. 2025年度 適格認定(家計)による 支援区分見直し |
2025年 10月 | 2025年1月1日~ 2025年8月31日 |
2025年10月25日 |
| オ. 2025年度秋の在学定期(二次)採用 | 2025年 10月 | 2025年1月1日~ 2025年8月31日 |
2025年10月25日 |
【注】提出期限に間に合わない場合等は学生課へご相談ください
3.本取扱いの適用対象となる判定
(1) 修学支援新制度における多子世帯に該当するかの判定
本取扱いは、2025年4月以降の支援に係る全ての判定が対象となります。
「扶養する子」の数が2人以下と判定されていた方が、本取扱いにより「扶養する子」の数が3人以上となれば、多子世帯に該当すると判定されうることとなります。
※ 修学支援新制度において「多子世帯」に該当するには、「扶養する子」の数が3人以上であることに加え、学生等本人が生計維持者の「扶養する子」である必要があります。前者に該当しても後者に該当しなければ「多子世帯」とは判定されません。
(2) 貸与奨学金家計基準における「多子控除」
本取扱いは、2025年4月以降の貸与奨学金申込に係る選考から対象となります。
貸与奨学金家計基準における「多子控除」の控除額の算定において、本取扱いにより子の数が3人以上となる場合、2人を超える子の数に応じて控除額が増加します。そのため、遡って第一種奨学生や第二種奨学生となる場合があります。
※ 貸与奨学金家計基準における「多子控除」は、学生等本人が生計維持者の「扶養する子」であるかを問わず、2人を超える子の数に応じて控除額を算定します。
※ 修学支援新制度利用中の第一種奨学金は、併給調整により減額された貸与額となります。
※ 第一種奨学金に不採用だった第二種奨学生が、本取扱いの申告を行い、遡って第一種奨学金に採用となる場合、併用貸与の基準を満たさないことにより第二種奨学金の貸与を受けることができない場合があります。
4.必要書類
(1)『新たに生まれた子等』の数の申告書 【第2版】
学生課で配付しますので、受け取りに来てください。
(2)本件の対象となることを示す公的証明書類の写し等(コピー可)
(1)の申告書には、以下①~③全ての書類の添付が必要です(必要な証明書類は(1)の申告書にも記載しています)。
①世帯全員の住民票写し(直近3か月以内に発行された、個人番号部分を非表示としたもの)
※ 現在の生計維持者が生計を一にする全員分の住民票が必要です。現在の生計維持者と扶養する子の住民登録地が異なる場合はそれぞれの自治体発行の住民票の添付が必要となります。
②戸籍謄本写し等、事由及び事由発生日が確認できる公的証明書類
※ 離婚の場合は戸籍謄本の写し、死別の場合は住民票除票の写し又は戸籍謄本の写し。
その際、事由の発生日が明確に記載されていること(例:離婚日)。
※ 暴力等から避難している場合は、自治体・警察発行の保護または避難証明書のコピー。
※ 生計維持者の行方不明・意識不明等により、扶養者の変更が生じていない場合は、自治体・警察発行の行方不明者届受理証明や主治医による診断書のコピー。
③生計維持者が受給する児童手当額改訂通知書等のコピー等、現在の生計維持者が3人以上の子供を扶養していることが確認できる公的証明書類
※ 児童手当では、生計費を負担している22歳までの児童の兄姉等を含めて第3子以降のカウントをしており、「第3子以降」がいることで「扶養する子」の数の確認をします。
※ 児童手当を受給していない場合は、現在の生計維持者及び「扶養する子」全員分の健康保険証(有効期限内に限る)の表面のコピー(マイナ保険証利用に切り替えている場合は、保険者が発行する被保険者資格証明書のコピー)。
以上
お問い合わせ等は学生課までご連絡ください。
大阪大谷大学 学生課